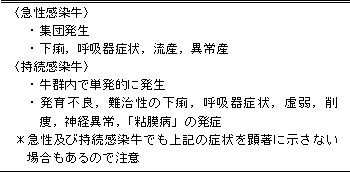![]()
|
牛ウイルス性下痢病(BVD)の現状と今後の課題
迫田義博†(北海道大学大学院獣医学研究科准教授)
 1 は じ め に 1 は じ め に牛ウイルス性下痢病(BVD)と聞くとその名の通り牛に下痢や粘膜病を引き起こすウイルス病と思われがちであるが,実際の症状は多様である.これまで見過ごされがちであったこの病気に対して,北海道の現場獣医師を中心に「本気の取り組み」がスタートしている.BVDとはどういう病気か,そしてBVD対策の基本と北海道における取り組みの現状,そして本病のコントロールのための今後の展望について解説したいと思う. |
|||
| 2 国内でのBVDの発生状況 家畜衛生統計によると年間のBVDの発生頭数は全国で120頭程度であり,この大半は臨床症状を示し摘発された持続感染牛や粘膜病発症牛である.しかし,急性感染や一見健康に見える持続感染牛が存在することを考えると,この数は氷山の一角であると思われる.後述するようにBVDに対する現場の意識や診断技術の向上によりBVDは「わかる病気」になりつつあり,摘発件数も増加傾向にある.BVDウイルスはその遺伝子配列から1型と2型に分類される.我々は,国内の発生の85%が1型,15%が2型のウイルスが原因であることを報告している.また,国内で分離される1型ウイルスと2型ウイルスの病原性は同程度であり,アメリカやカナダで報告されている高病原性の2型BVDウイルスは現在までのところ存在しない.ちなみに,BVDウイルスの感染が報告されている動物として牛以外に山羊,緬羊,豚,さらに国外ではキリンやシカ等の野生動物も含まれる. 国内で分離されるBVDウイルスの大半は持続感染牛から分離されている.生涯ウイルスを排泄し続ける持続感染牛は,発育不良,難治性の下痢,呼吸器症状等の症状を示すことで摘発される(表1).しかし,同居牛検査で摘発される持続感染牛は一般に無症状であり,臨床症状のみで持続感染牛と診断することは困難である.よって,BVDの診断には家畜保健衛生所におけるウイルス学的検査が必須となる.
|
|||
| 3 なぜ今BVDか 日本で初めてBVDが報告されたのは1967年である.それから現在に至るまで,BVDは継続的に発生が報告されてきた.では,なぜ今BVDが注目されるようになったのか.それにはいくつかの要因がある. (1)診断技術の向上 BVDウイルスは細胞に感染しても培養細胞を壊すことなく増殖する(非細胞病原性)ものが大半であり,その診断は容易ではない.そのため以前は,ウイルスの検出に干渉法と呼ばれる特殊な技術が利用されてきた.現在は特異抗体を用いたウイルス抗原の検出や,PCRを用いたウイルス遺伝子の検出,さらにBVDウイルスの感染の識別が容易な培養細胞の普及により,家畜保健衛生所で容易に診断できる病気となりつつある.家畜保健衛生所で分離されたウイルスは,動物衛生研究所や北海道大学が中心となって抗原性や遺伝子解析を行い,防疫対策に役立つ情報を現場にフィードバックしている. (2)現場における本疾病の理解 北海道においてBVDに注目が集まりだしたのは平成13年頃からである.NOSAIをはじめとした現場獣医師はこれまでも表1に示す牛を野外で経験していたが,この問題の原因にBVDを疑う意識が低かった.しかし現場獣医師と家畜保健衛生所の積極的な取り組みの中で,BVDという病気の実態がわかってきた.これらの取り組みを後押しするように大動物臨床研究会においても平成16年からの3年間,「BVDの撲滅」を研究会の主たるテーマとして活発な議論,啓蒙活動が行われた.さらに,国内メーカー2社からBVDウイルス2型の抗原を含むワクチンが発売されたことも現場の注目を集めることに拍車をかけた.現在,BVDに対する注目は北海道にとどまらず,全国的な盛り上がりを見せている.それを端的に物語るのは,学術集会や家畜保健衛生所の業績発表会におけるBVDに関する演題数の急激な増加である.このBVD旋風を一時的な盛り上がりとせず,高い意識を継続するよう,関係機関のより一層の努力が求められている. |